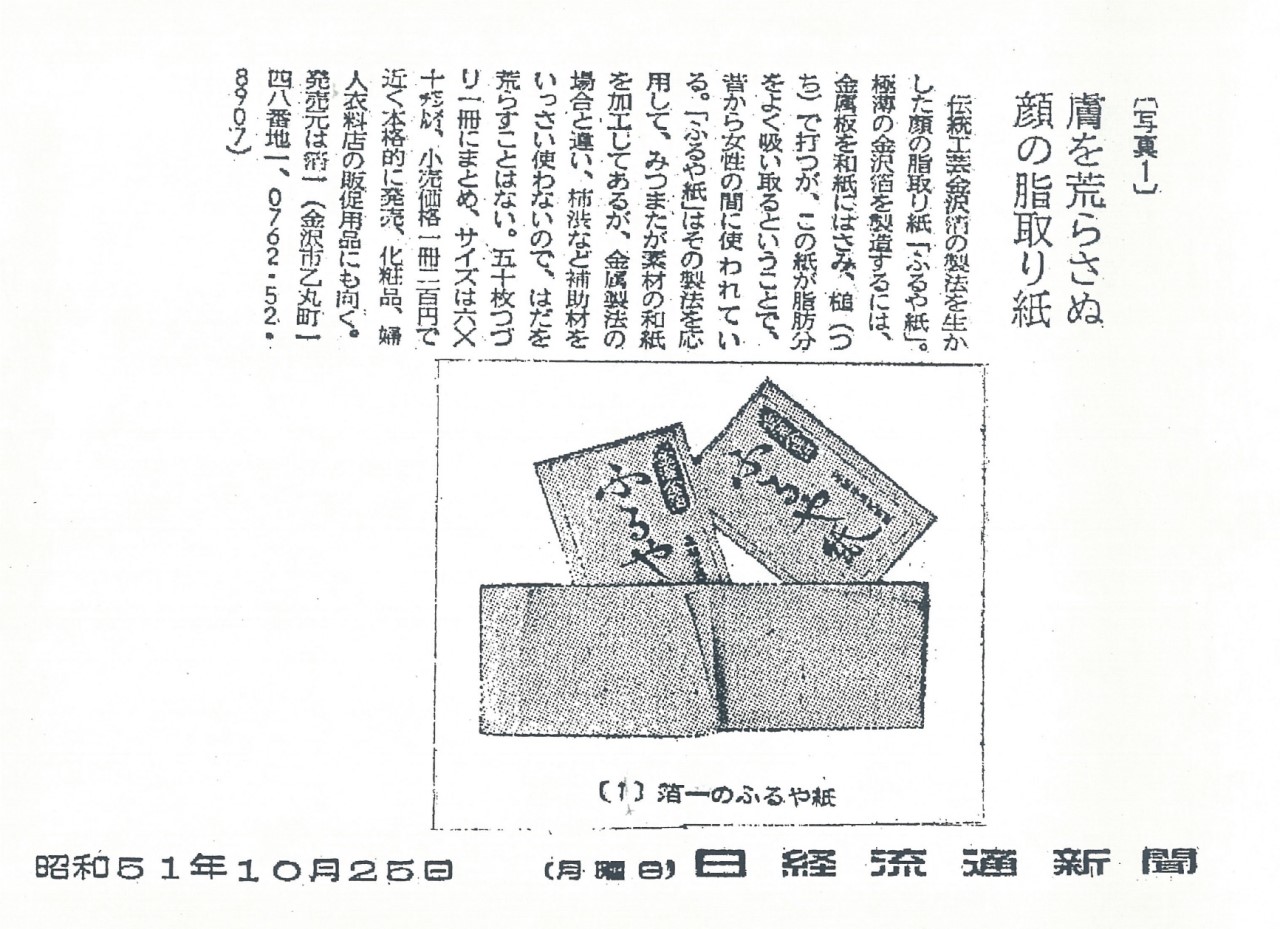時代の変化とともに減っていった、ふるや紙。
昭和40年代に、箔打ちは、昔ながらの「縁付」から、現代的な「断切」へと変わっていきました。
このことで、金沢市においては金箔の生産性が飛躍的に高まり、独占的な地位を占めるようにもなりました。
一方で、困り始めたのは、使い終えた箔打ち紙を「化粧紙」として仕入れていた商人たちでした。縁付金箔を打つのに使う箔打ち紙は、使い終えると「ふるや紙」と呼ばれ、皮脂をよく吸い取ることから、化粧紙として京都の芸妓や役者たちの間で好まれていました。断ち切り箔では和紙ではなく、グラシン紙を使うため、こうした需要を満たせなくなっていたのです。